





- Blog記事一覧 -冷え | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧
冷え | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

先日、40歳代男性の方が、腰痛を訴えて来院されました。
特に、朝、起きたときに腰の痛みを感じるとのこと。
検査させていただくと、足の筋肉の硬さが顕著だったため、この要因となる思い当たる生活習慣はないですか?お聞きしたところ、
「そういえば、夜が暑いから、クーラーをつけて寝てるんですけど、朝、起きたら、足がすごく冷えてますね」
とお答えいただきました。
今回の実例は、冷房病の一つとして、足が冷えることによって、腰痛が発症した可能性があります。
そこで今回は、クーラーの効いた部屋で睡眠中に足が冷えることで腰痛が発症する理由とその予防法について紹介させていただきます。
このブログを読んでいただくことで、暑い夏の夜にクーラーをかけて寝ても、寝起きに腰の痛みで悩まされることを解消できます。

今回、ご相談いただいた実例は、クーラーによって足が冷えて、それが腰痛につながったというものです。
ですが、夜、寝ているときには、クーラーは使用しない方がいいというわけではないのです。
なぜなら、夏の暑い夜に、クーラーを使うことは、快適な睡眠を得るために非常に重要です。
その理由として、夏の夜の気温も湿度も高い室内の環境で寝ることは、体温の調節が難しくなり、睡眠の質が低下する可能性があるためです。
睡眠の質が低下すると、寝ている間におこなわれる体の回復ができず、夏バテや夏風邪などの夏に起きがちな体調の不調につながります。
また、寝ている間に、暑い室内で寝ることで、体温の過度の上昇や発汗による体の水分の消失で、熱中症や脱水症などが発症して、生命の危機につながる恐れがあります。
実際、先日も、クーラーを我慢して寝ておられた方が、脱水症で両足の筋肉がけいれんして、動けなくなったという怖い経験談をお聞きしました。
確かに、クーラーは過度に浴びると、体調に影響しますが、クーラーの使用をゼロにするのではなく、うまく使うことで、暑い夏を快適に過ごすことができます。

クーラーの冷気が体に当たることで、筋肉が冷えます。
特に、夏は、パジャマが半袖半ズボンとなることが多く、手足がむきだしとなるため、冷気に当たりやすく、手や足の筋肉が過度に冷やされることがあります。
クーラーの冷えにより、血管が縮み、血流が悪くなるため、筋肉の硬さが増します。
足の筋肉は、腰と直結しているため、足の筋肉が硬いと、腰の動きを制限し、腰に痛みが発生する要因とになります。

夏にクーラーをかけて寝ることで、足が冷えて、それが寝起きに腰の痛みが発生しやすくなります。
それを予防するための方法を、以下で紹介させていただきます。
寝室の温度を、「26℃」程度に設定し、室内が冷えすぎないように心がけてください。
これにより、過度な冷気によって、足の冷えることから守ることができ、結果、腰痛予防につながります 。
冷気が直接体に当たらないように、エアコンの風向きを天井に向けるのがベストです。
天井に流れた冷たい空気は、下に降りる性質があるため、部屋全体に均等に広がり、室内の冷えすぎを防ぎます。
部屋の構造やエアコンの位置によって、冷気が均等に行き渡らない場合は、サーキューレーターや扇風機を利用して調整してください。
風速は、低風量に設定してください。強すぎる冷たい風は、体に当たると、冷えすぎるだけではなく、睡眠の質を低下させるという研究報告もされています。
クーラーで冷えるすぎるのを予防するために、タイマーで睡眠の途中でスイッチを切る設定をされる方もいらっしゃいます。
タイマーが切れると、室温が上がって、寝苦しくなり、結局、起きてまたつけなおすこともあるようです。
寝ている時の体温が最低になるのは、午前4時から5時の間にです。
ですので、タイマーを設定するなら、体温が自然と下がる午前4時あたりに設定することで、寝苦しさからも、足が過度に冷えることも予防できて、なおかつ、睡眠の質が向上する可能性があります。
クーラーが効いた部屋で腰痛を予防するためには、パジャマの選び方が重要です。
特に、下半身が冷えることが腰痛の要因となることがあるため、下だけでも長ズボンのパジャマを着用することがおすすめです。
というのも、長ズボンのパジャマを着ることで、足元から腰までをしっかり保温でき、筋肉の緊張や血行の不良を防ぎます 。
クーラーの効いた部屋ではく長ズボンのパジャマとして、綿やフランネル、モダールなどの柔らかくて保温性があり、肌触りの良い素材を選びましょう。
また、ゆったりとしたデザインの長ズボンパジャマを選ぶことで、血行を妨げずにリラックスできます。

寝起きに腰の痛みを感じているのに、無理に動くと、余計に痛みが増し、場合によっては、ぎっくり腰が発生する恐れがあります。
寝起きの腰痛を解消する最も手取り早い方法は、朝風呂に入って、体を温め、エアコンで冷えた体を温めることです。
湯船につかるのが難しく、シャワーを浴びることが可能でしたら、42度程度の少し熱めに設定した温度のお湯を集中的に、腰や足に当ててみてください。

夏の暑い夜にクーラーを使うことは、快適な睡眠には欠かせません。
しかし、クーラーの冷気が、足の筋肉を冷やし、それが腰痛を引き起こすことがあります。
この問題を防ぐためには、クーラーの設定温度や風向きの調整、パジャマの工夫、必要です。これらの対策を実践することで、クーラーによる冷房病を予防し、快適な睡眠を保つことができます。
そのために、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。
それでも、クーラーによって足が冷えることで起きる腰の痛みが解消されないようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。
当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。
当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。
そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。
また、他に、腰痛への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。
監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

梅雨も終わり、暑い夏に突入する時期になりました。
この時期、本来、減少するかと思われる風邪や新型コロナウイルスなどへの感染ですが、全国的に増加傾向にあると報告されています。
当院でも実際に、そういった感染症のために、お仕事や学校を休むなど、日常生活に支障がでたり、ご家族に心配をかけてしまうお話をよくお聞きします。
そこで今回は、夏の時期に、風邪や新型コロナウイルスなどに感染する理由とその予防法について紹介させていただきます。
このブログを読んでいただくことで、健康に夏を過ごすことができます。

本来は、寒い冬に、コロナウイルスや風邪ウイルスによる感染者数が増加する傾向にあります。
しかし、それに反して、夏に増加する傾向にあるのは、一見、不思議に思えるかもしれませんが、いくつかの理由が考えられます。
以下に、そのメカニズムを紹介させていただきます。
夏場は、エアコンを多用するため、室内の空気が乾燥しやすくなります。
エアコンによって乾燥した室内は、多くのウイルスにとって、空気中で長く生きやすく、増殖しやすい環境です。
さらに、エヤコンによって乾燥した室内に、夏の暑さを避けるために、長時間、とどまることで、のどの粘膜を乾燥させます。
そのために、のどを通過するウイルスを粘膜がからみとって体への侵入を防御する機能が弱まり、その結果、ウイルスが体内に侵入しやすくなります。
つまり、エアコンの使用による室内の乾燥が、ウイルスの増加とのど防御機のを低下させ、夏に感染症が増えるます 。
夏の暑さは、体温を調節するために内臓や脳などの稼働を強いることで、体に多くのストレスを与え、疲労しやすくなります。
疲労がたまると、細胞を活動させるエネルギーの不足を起こし、免疫細胞の力が弱まります。
また、暑さによるストレスは、ストレスホルモンの分泌を増加させ、このホルモンは、免疫の機能を抑制する働きがあります。
こういった理由により、夏の暑さのストレスによって体が疲労すると、免疫の機能がうまく働かず、感染症が増加する要因です。

暑い夏に、風邪や新型コロナウイルスなどの感染予防の方法を以下で紹介させていただきます。

エアコンを使用する際には、空気が乾燥しやすくなるため、適度な湿度を保つ必要があります。
室内の湿度は、40〜60%に保つことが理想です。
そのために、室内で加湿器を稼働させたりやぬれタオルを干すなどして、湿度計などで数値を確認しながら、湿度を調整することをおすすめします。
また、外が暑いと部屋を閉めっぱなしになり、室内のウイルス濃度が上がります。
空気清浄機の稼働や、1時間に1回を目安に窓やドアを開けて、換気を定期的におこなうことで、室内のウイルスの濃度を下げてください。

手洗いやうがいは、感染症対策の基本です。
外出先から帰宅した際や食事前後、公共の場を利用した後には、石けんと流水で20秒以上手を洗うことをおすすめします。
うがいは、普段は、普通のお水でいいので、まずは、口の中をゆすいで、口の中のウイルスや細菌をはきだしてから、その後に、ガラガラとのどをゆすぐようにうがいをおこなってください。

夏は、エアコンが効いた部屋に、長時間、いるためや冷たい飲料を飲む機会が増えるため、体の深部が冷えて体温が低下している方が少なくありません。
しかし、夏は気温が高いため、入浴はシャワーで済ませて、体を温める機会が減りがちです。
1日1回でも、体の表面の温度を一時的に上昇させるシャワーではなく、体全体の深部の体温を持続的に上昇させる湯船に入ることをおすすめします。
深部体温の上昇は、リラックスや免疫機能の向上を促しますので、感染症予防として、湯船につかることは有効です。
夏の時期は、湯船の温度をぬるめの38℃〜40℃にすることが適しています。
また、長時間の入浴は、体に負担をかけるため、15分〜20分程度を目安にしてください。

夏は気温と湿度が高く体が疲れやすい時期のため、腸の機能を整えることは、全身の免疫力を高めるためにも非常に重要です。
なぜなら、小腸には、全身の免疫細胞の70%が存在しているからです。
夏に体が適正に免疫機能が活動するために腸を整える食生活について、以下で紹介していきます。

腸が消化・吸収などする活動のためには、水分という媒介が必要です。
夏は汗をかきやすく、体内の水分が失われやすいため、十分な水分を摂取して、腸へ補給することが重要です。
1日の基本的な水分摂取量は、1.5〜2リットルです。そのほかに、食事に含まれる水分として1リットル、さらに追加で、夏季の増加量0.5〜1リットルが望ましいです。
一気に飲むのではなく、一回につき200ml程度を、1日に何回かに分けて、こまめに摂取してください。
冷やした飲料を飲み過ぎると、冷えて腸の活動が低下するため、適度に温かい飲料や常温のものを摂取することを心がけてください。

腸の健康には、バランスの取れた食事が欠かせません。
特に、食物繊維や発酵食品を積極的にとることで大切です。
食物繊維としては、野菜、果物、全粒穀物、豆類など。
発酵食品は、ヨーグルト、キムチ、納豆、みそなど。
こういった食品をとることで、腸内の善玉菌のが増えて、腸が正常に活動することが促されます。

睡眠の質と免疫力との関係は、非常に密接です。
睡眠中に体は、免疫システムを修復し、強化します。特に、深く眠れることで、体は免疫細胞を生成し、感染と戦うための抗体を作ります。
ですので、夏の感染症対策には、睡眠の質を上げる必要があります。
睡眠の質を上げるには、
・エアコンや扇風機で寝室の温度を約20〜22度に保つ
・寝る2時間前には電子機器の使用を控える
・毎日、同じ時間に寝て、同じ時間に起きる
・読書、音楽鑑賞、温かい風呂などでリラックスできる活動するを
などといったことを心がけることで、睡眠の質が上がり、その結果、免疫機能も正常に働く体を作れます。

夏の感染症対策は、適切な室内環境の管理、手洗いと消毒の徹底、湯船での体温調整、バランスの取れた食事、質の高い睡眠といった日常の小さな習慣の積み重ねでおこなえます。
これらの取り組みが、免疫力が正常に働き、健康な夏を過ごすための基盤づくりとして、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。
それでも夏の暑さによる感染症への不安が解消されないようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。
当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。
当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。
そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。
また、他に、感染症に関する体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。
監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇

7月に入り夏のおとずれとともに、多くの家庭では冷房の使用が増えてきます。
特に、犬を室内で飼っておられるご高齢の方の家庭では、夏の室内温度の管理が、犬にとっても飼い主の方にとっても健康の鍵です。
一般的に、こういったご家庭では、室内で飼っておられる犬のために、一日中、冷房をかけて、飼い主の方が室内で一緒に過ごされていることが多いと思われます。
そうすると、どうしても、飼い主のご高齢の方の体も冷え切って、「冷房病」とも呼ばれる肩こりやけん怠感などが発生し、体調を崩しやすくなります。
冷房病が発症したからといっても、飼っている犬や飼い主ご本人が、熱中症にならないように、家のクーラーをとめるわけにもいきません。
そこで今回は、長時間、ペットのために冷房が効いた環境で過ごされているご高齢の飼い主の方が冷房病が発症する理由、その予防法について紹介させていただきます。
このブログを読んでいただくことで、暑い夏を冷房の効いた部屋で、室内で飼っている犬とご高齢の飼い主の方が、健康を共存しながら過ごせます。

冷房病とは、エアコンの過度な使用にり、体が冷えすぎることによって引き起こされる症状を総称したものです。
主な症状には、肩こり、頭痛、けん怠感、消化不良などがあります。
ご高齢の方が、長時間、冷房の効いた室内で室内で飼っている犬と一緒に過ごすことで、冷房病の発症を発症する理由は、以下のことが考えられます。
人間は、天気や気温の変化に対して、自律神経によって自動的に適応しています。
年齢を重ねると、自律神経の機能や反応が遅くなり、環境の変化に体がついていかなくなります。
そういったことから、夏に冷房をかけて外部からの急激な冷気を受ける環境に、ご高齢の方が左右されると、筋肉や内臓を機能させるための適切な体温が維持されず、冷房病の症状が現れやすくなります。
多くの場合、ご高齢の方は愛犬と一緒に長時間を室内で過ごされるため、ペットのために冷房をかけていることが多いです。
犬の体温調節能力も人間より低いため、飼っている犬に合わせて、室内温度を調整することで、飼い主のご高齢の方には合わない過度に冷えた環境下で過ごす時間が長くなります。
そのため、体が冷え切り、冷房病が発症するリスクが増大している可能性があります。

室内で犬を飼っておられる飼い主の高齢の方が、冷房病を予防するためには、以下の対策が有効です。
夏における室内の温度を適切に設定することは重要です。
一般的には、外気温との差が3〜4℃程度に保つことが推奨されています。
また、設定する温度としては、25〜28℃が目安とされ、室内と室外の温度の差が少ない環境を保つことが理想です。
室内の湿度も健康に大きな影響を与えます。
夏にクーラーをかけすぎて湿度が低くなると空気が乾燥し感染症になりやすく、逆に高すぎるとカビやダニの発生してアレルギーが増加します。
適度な湿度としては、40〜60%を維持することが望ましいです。
長時間、冷房の効いた部屋で、同じ姿勢で過ごすと、筋肉のこわばりや血流が悪化して、体温の低下の要因です。
冷房が効いた室内でも結構ですので、ラジオ体操やその場で足踏みなど、定期的に立ち上がって軽く運動してください。
体に刺激を入れることで、体温が上昇したり血行の促進し、冷房病の発症を予防できます。
暑い時期は、ついつい、のごしの良い冷たい食べ物や飲み物を摂取しがちです。
そうすると冷房で体の外部から冷えていることに加えて、体の内部から冷やすこととなり、冷房病のリスクが高まります。
ですので、温かい食事や飲み物を摂取することを、意識的に心がけていただいて、体を内部から温めて、冷房による体の冷えを予防してください。
冷たい冷房の風に皮ふがさらされると、体温が奪えわれて体が冷えます。
冷房が効いた室内では、カーディガンやひざ掛け・タオルなどで、首、手首、足首などを覆ってください。
それによって、体が保温されて、冷房病を防げます。

気象庁が日本動物愛護協会の協力のもと、「イヌ・ネコの熱中症予防対策マニュアル」の小冊子が作成されています。
その小冊子は、お近くの動物病院で無料配布されていますし、以下のリンクでもダウンロードできます。
https://www.jwa.or.jp/wp-content/uploads/2020/08/b50dd7324cb64b285b4c8ac471021dee.pdf
ガイドラインを参考にしていただいて、必要以上に室内を冷やさないとかグッズの利用などで、人にも犬にも無理がない、共存できる夏に最適な室内環境を整えてください。

暑い季節は、飼われている犬や一緒に過ごされているご高齢の方にとって、適切な冷房の利用して、熱中症を予防することは重要です。
それと同時に、冷房による体への影響を軽減する対策をすることで、冷房病を回避し体調を維持して夏を快適に過ごせます。
そのための方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。
それでも長時間、冷房にあたることで体の不調のお悩みが解消されないようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。
当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。
当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。
そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。
また、他に、冷房病の症状でもある肩こりや冷えによるけん怠感への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。
監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

田植えのシーズンがもうすぐやってきます。
田植え自体も大変なのですが、その前の準備である、ため池や用水路の掃除、あぜの草刈り、田んぼのしろかき、などはさらに大変だというお話をよくお聞きします。
そして、そのどれも重労働のため、田植えの準備作業をおこなった後の就寝中に、ふくらはぎがつる、いわゆる、
「こむら返り」
が発生しやする方が少なくありません。
そこで今回は、田植えの準備作業した日の就寝中にこむら返りが発症しやすい理由とその予防、こむら返りが起きた際のなおし方について紹介させていただきます。
このブログを読んでいただくことで、こむら返りによって痛い思いをすることを解消できます。

こむら返りとは、ふくらはぎの筋肉にけいれんが起きることです。
筋肉がけいれんするということは、ざっくりいえば、「筋肉の伸び縮みを調整するセンサーの誤作動」です。
筋肉の伸び縮みを調整するための命令をだす中枢は、背骨の中を通る神経の束である「脊髄(せきずい)」がおこないます。
その脊髄に、筋肉の状態の情報を送るセンサーが、「筋肉の中」と「筋肉の端っこにある腱」にあります。
「脊髄(せきずい)」・「筋肉の中のセンサー」・「筋肉の端っこにある腱のセンサー」が互いに働きあって、筋肉が調整されます。
例えば、
①寝ているときに背伸びなどをしてふくらはぎの筋肉が伸びる
⬇︎
②筋肉のセンサーが「ふくらはぎの筋肉が伸びすぎている!」という情報を発信
⬇︎
③脊髄がその情報を受けて「ふくらはぎの筋肉を縮めろ!」と命令
⬇︎
④ふくらはぎの筋肉が縮む
⬇︎
⑤筋肉の端にある腱の中のセンサーが「ふくらはぎの筋肉が縮みすぎている!」という情報を発信
⬇︎
⑥脊髄がその情報を受けて「ふくらはぎの筋肉を緩めろ!」と命令
というループが起きて、筋肉の状態を調整されています。
このループの中で、『⑤筋肉の端にある腱の中のセンサーが「ふくらはぎの筋肉が縮みすぎている!」という情報を発信』の機能が、
・水分不足
・血流不足
・冷え
・筋肉疲労
・筋肉量の低下
・活動量の低下
・薬の副作用
・糖尿や腎臓病
などの要因によって機能が低下する場合があります。
そうすると、『③脊髄がその情報を受けて「ふくらはぎの筋肉を縮めろ!」と命令』が止めることができず、筋肉が縮む状態が強くなりすぎて、ついには、ふくらはぎの筋肉がけいれんを起こします。
これが、「こむら返り」です。
特に、田植えの準備は、筋肉の疲労や水分不足が著しい場合が多くなるため、こむら返りが起こりやすくなります。

田植えの準備作業をした日の就寝中に、こむら返りが発症を予防するための方法を以下で紹介させていただきます。

体から水分が失われると、筋肉の情報を脊髄に伝える筋肉の中のセンサーや筋肉の端っこにある腱のセンサーが誤作動を起こしやすくなります。
日中の田植えの準備作業で発汗することで、体の水分が失われます。
また、睡眠中でも300ミリリットルの水分が失われるとされています。
ですので、就寝前には、意識して水分をとてください。お酒を飲むと、アルコールの分解に体の水分を使います。
田植えの準備作業後にお酒を飲んだ場合は、摂取したお酒の量分以上の水もしくはノンカフェインの飲料を摂取してください。

筋肉の冷えや血流不足でも、筋肉の情報を脊髄に伝える筋肉の中のセンサーや筋肉の端っこにある腱のセンサーが誤作動を起こしやすくなります。
田植えの準備作業後は、シャワーで終わらさずに、湯船にゆっくりつかって、体を温めてください。
また、寝る際には、ふくらはぎが冷えないように、パジャマを長ズボンにしたり、レッグウォーマーを履くなどして保温を心がけてください。

就寝中のこむら返りは、寝ているときの何気ない背伸びで、つま先を伸ばすことがきっかけで起こることが多い。
つま先が伸ばしにくいように、足首にサポーターをはいたり、包帯を巻いたりして、足首を軽く固定してください。

寝る前に、両手をふくらはぎに当てて、上下に軽く優しくさすってください。
そうすることで、ふくらはぎの筋肉がリラックスして、就寝中に刺激を受けてもこむら返りが起こりにくくなります。

芍薬甘草湯は筋肉を緩め、けいれんを収め、血管を広げて血量を増やすことで、筋肉の痛みを和らげ、こむら返りに顕著な効果をもたらす漢方薬です。
田植えの準備作業で、ご自身の筋肉の疲労が予想される場合は、病院の方で処方してもらってください。
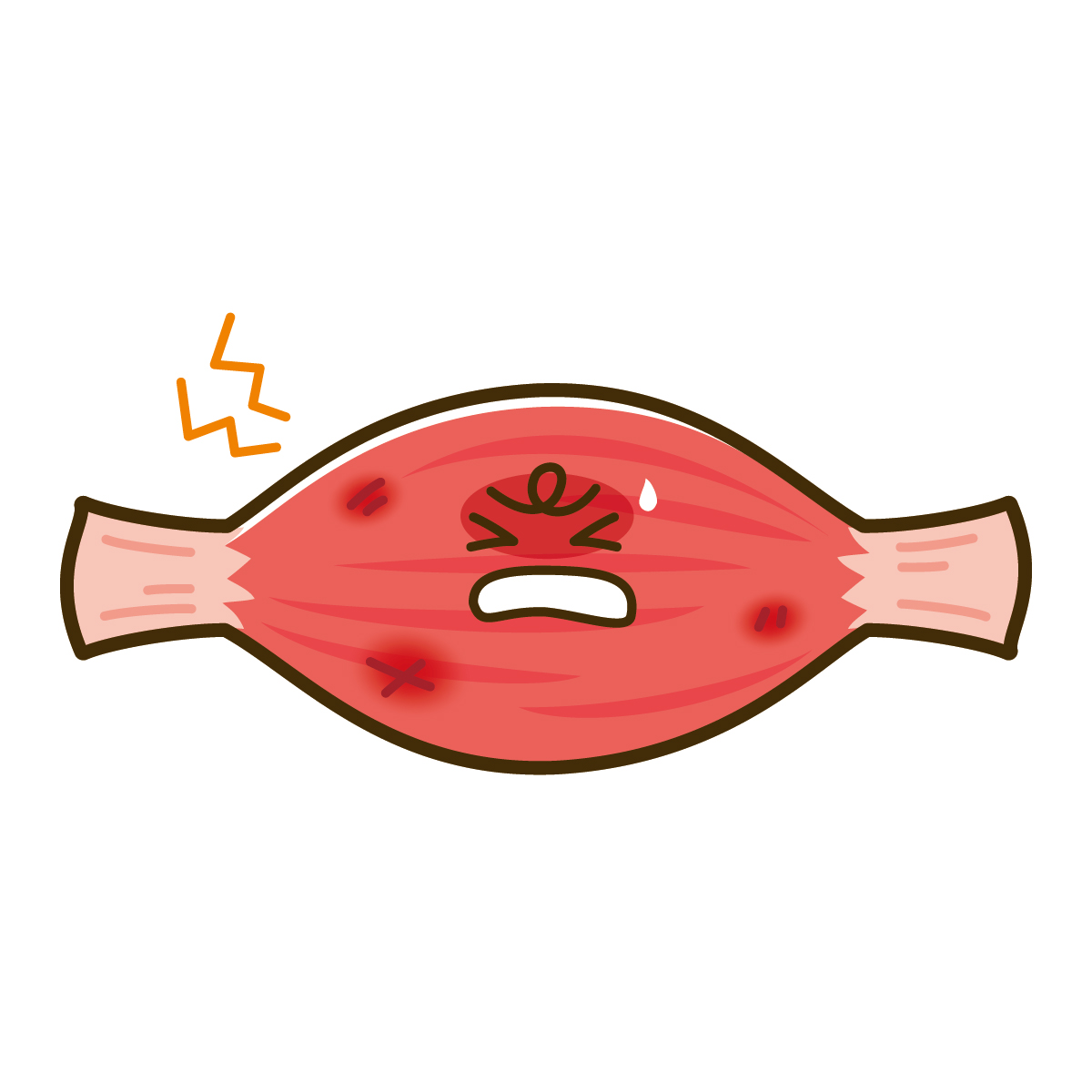
寝ているときに、こむら返りが起こった対処法は、「ふくらはぎをゆっくり優しく伸ばす」が有効です。
その方法は、
・足を伸ばして、手でつま先を持ち、体の方に引っ張り、ふくらはぎをゆっくり伸ばす

・タオルと爪先にかけて、体の方に引っ張り、ふくらはぎをゆっくり伸ばす

・壁に足の裏を押し付けて、ふくらはぎをゆっくり伸ばす

という感じで、やりやすい方法でおこなってください。
ふくらはぎを伸ばしても、こむら返りが治らないようでしたら、
・両手でふくらはぎを包んで優しくさする
・水や経口補水飲料などで水分をとる
・いったん足首を伸ばしてふくらはぎを縮めてから、もう一度、ふくらはぎを伸ばす
・お風呂に入ったりシャワーふくらはぎにあてて温める
ことを試してください。
こむら返りの発作が収まっても、それによって筋肉痛や肉離れが起こり、ふくらはぎの痛みが続く場合があります。
その痛みの度合いが、こむら返りをしてから1週以上、変わらないようでしたら、お近くの病院や治療院を受診して、診断と処置を受けられることをおすすめします。

私も少し田植えをお手伝いさせていただいたことがあるのですが、田植えに関わる作業をした後の2〜3日は筋肉痛で思うように動けず、お米作りってこんなに大変なのかと思い知った経験があります。
そんな大変なお米づくりは、初夏から収穫する秋まで、大変な作業が続きます。
まず、そのスタートの作業となる田植えの準備期間に、こむら返りを予防することで、スムーズに作業に当たっていただきたい。
そのための方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。
それでも田植えの準備作業をした日の就寝中にこむら返りが起きやすいお悩みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。
当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。
当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。
そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。
また、他に、農作業による体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。
監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

5月も中旬ですが、過ごしやすい季節ではありますが、朝晩の寒暖差が激しい時期でもあります。
こういった気温の変動がある時期は、それに体が対応しきれずに、いろいろな体の不調を起こしやすい季節でもあります。
この季節に起こりやすい体の不調の一つとして、
「寝違え」
です。
寝違えが発症すると、顔を下に向けたり、腕を使っての作業をするたびに、首や肩に痛みが走り、仕事や家事などの日常生活に支障がでます。
そこで今回は、寝違えが発症する要因や対処法などについて紹介させていただきます。
このブログを読んでいただくことで、寝違えの回復期間を早めることができます。

寝違えが発症する要因は、以下のことが考えられます。
枕や寝具が体の形状に合わなかったり、寝床でパートナーや子供、ペット、ぬいぐるみなどと一緒に寝ることで、首が不自然な角度で曲がるような睡眠姿勢となる場合があります。
そのために、首の関節や筋肉に負荷がかかりすぎるために発症します。
睡眠中は、血流や体温が下がり、動きも少なくなるため、筋肉は硬くなりやすい。
筋肉が硬い状態で、朝、目覚めた際に、急に首を動かすことで、首の筋肉が引っ張られて、それに対応できずに痛みが発生する可能性が高まります。
日常的なストレスや肉体的な疲労、運動不足などにより、筋肉の緊張や筋力の低下により、頭の重さを支えることができず、寝違いが生じやすくなる。
日中に比べて、朝方は気温が低下します。首は寝る服に覆われずに、朝方の冷たい空気に皮ふが直接触れやすいため、首が冷えやすくなります。
その結果、首周辺の筋肉が硬直し、寝違いが発生すやすくなる。

一般的な寝違えは、そのままにしておいても、1週間ほどで徐々に痛みが軽減されます。
1週間以上、寝違えが軽減せずに、寝違えが発症した直後と同じ程度の痛みが続くようでしたら、ヘルニアや腫瘍などの他の重篤な病気が隠れている場合があります。
その場合は、お近くの病院で精密検査を受けられることをおすすめします。

寝違えを発症した直後に行ってはいけないことは、
・首のマッサージ
・首のストレッチ
です。寝違えを起こしているということは、首の関節や筋肉が炎症を起こしている可能性が高いです。
その首に直接、強い刺激を入れることで、首周辺の炎症が増加し、かえって症状が悪化する場合があります。

寝違えによって、首の周辺の組織の損傷します。
それをなおすために、首の損傷した部分に、血液を通して、栄養な酸素を提供して、老廃物を回収する必要があります。
そのために、お風呂に入り首を温めたり、首にタオルやスカーフを巻いて保温することをおすすめします。
寝違えの発症直後の1日目で、首を触ると熱く感じて、どうしても痛みがきついようでしたら、アイスパックで冷やしてください。
寝違えが発症して、2日目以降は、首を温めた方が治りが早まります。

寝違えの際には、首を直接刺激すると、かえって痛みが増加することを、「寝違えが起こった際にやってはいけないこと」の章で紹介させていただきました。
首の筋肉や関節へ直接刺激するのではなく、首の筋肉や関節に連携している遠方の部分から刺激を入れることで、寝違えを軽減する効果があります。
そのためのストレッチを以下で紹介させていただきます。
壁の前に立ち、指を床方向に向けるように手首を曲げて、手のひらを壁に当ててください。

壁に当てた手と反対側に体をねじって、腕の力コブあたりが伸びるのを感じたら、10秒間、キープしてください。

反対側の腕も同じようにおこなってください。
壁の横たち、肘を曲げた状態で腕を肩の高さまで上げて、前腕の小指側を壁につけます。

壁に当てた前腕と反対側に体をねじって、壁につけた前腕側の胸のあたりが伸びるのを感じたら、10秒間、キープしてください。

反対側の腕も同じようにおこなってください。

寝違いに効果があるツボは、「落沈(らくちん)」です。
このツボは、手の甲側の人差し指と中指の骨の交わる所に位置します。

寝違えによって首が動きづらくなると、肉体的な痛みだけでなく、不安やイライラなど精神的な不調も引き起こします。
放置しても徐々になおってはいく症状とはいえ、日常生活を送る上で、心身に影響が大きいので、なるべく早く回復を促すべき症状です。
そのための方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。
それでも寝違えによる首の痛みのお悩みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。
当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。
当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像のことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。
そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。
また、他に、首の痛みへの対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。
監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広